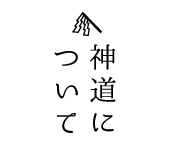神社Q&A
神社についてのさまざまな疑問にお答えします。質問をクリックすると、解答が表示されます。
Q.神社や家庭の神棚にある注連縄(しめなわ)の向きはどうしたらいいのですか?
注連縄(しめなわ)は一方が太く、もう一方が細くなっています。太い方が「元」、細い方が「末」となります。一般的には神社や家庭では太い方を向かって右に、細い方を向かって左にします。
但し、神社や地域によっては、これとは反対の向きにすることもあります。古くからそのようにされていた場合は、その土地ではそれが伝統であり、間違いではありません。
また、縄のない方は「左ない」が一般的ですが、神社・地方の習慣によっては「右ない」と「左ない」を抱き合わせたものなどもあるようです。
「元」が右で「左ない」のものを図にすると次のようになります。

実際の社殿の写真は次のようなものです。

岡山縣護國神社(岡山市)
神社で一般的に取りつけられている注連縄
縄をなう方向が「左ない」で向かって右側が太いもの
(太さは少し微妙ですが)

吉備津彦神社(岡山市)
左ないと右ないを抱き合わせています
Q.注連縄(しめなわ)に付けてある紙は何ですか?
注連縄(しめなわ)には紙で作った飾りがついています。これを紙垂(しで)といいます。注連縄と紙垂は、ここからが神様に近い、神聖で清浄なところであることを示しています。

紙垂のつくり方
-
 任意の大きさの紙を左端を折り目にして二つに折ります。
任意の大きさの紙を左端を折り目にして二つに折ります。
このの写真は半紙を1/4に切って、二つ折りにしたものです。 -
 二つ折りにした紙に、上下互い違いに切れ目を入れます。
二つ折りにした紙に、上下互い違いに切れ目を入れます。 -
 2列目の部分を手前に折ります。
2列目の部分を手前に折ります。 -
 3列目の部分を手前に折ります。
3列目の部分を手前に折ります。 -
 4列目の部分を手前に折ります。
4列目の部分を手前に折ります。
Q.厄年ってなんですか?
「厄年」とは悪いことが身にふりかかりやすい年・人生の節目の年のことをいいます。
数え年で男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳が本厄、その前後を前厄・後厄といい、神社にお参りをして災厄を除けるために厄除(厄祓)をします。
厄年表
| 男性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|
24歳
|
25歳
|
26歳
|
|
41歳
|
42歳
|
43歳
|
|
60歳
|
61歳
|
62歳
|
| 女性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|
18歳
|
19歳
|
20歳
|
|
32歳
|
33歳
|
34歳
|
|
36歳
|
37歳
|
38歳
|
※数え年は、誕生日前の場合は2歳、誕生日を迎えている場合は1歳を足して計算します。
Q.厄年や七五三は数え年と満年齢のどちらでするのが良いのでしょうか?
数え年とは生まれたときを1歳として数えはじめ、初めて迎えた元旦に2歳となる年齢の数え方です。以後、元旦の度に1歳ずつ年齢を加算していきます。この方法では、日本人は1月1日に皆一斉に年を1つ取っていきます。極端な例では12月31日に生まれた子どもでも、生まれた次の日の1月1日には2歳になります。
今の感覚からすると少し変わっているように思えますが、旧暦には閏月というものがあります。例えば11月が「11月」と「閏11月」の二回ある年がありました。誕生日に年を取る考え方だと、「閏月」に生まれた人が正確に年をとる日に問題があったため「数え年」が考え出されたのかもしれません。
また、平成24年の1月1日から12月31日生まれの人はすべて、「辰年生まれ」というのも数え年の考え方です。

Q.初宮参りは何日目にするんですか?
赤ちゃんが初めて神社にお参りする初宮参りは、氏神さまに無事に誕生したことの奉告と御礼をし、氏子として健やかに成長することを祈るものです。
一般に男の子は生後31日目、女の子は33日目にお参りしますが、地域によって異なることもあります。子供の体調や天候などにも気を使い、最良の日を選んでお参りましょう。

Q.七五三って何のためにするんですか?
三歳の男女児、五歳の男児、七歳の女児が晴れ着をきて、神社にお参りをします。子供の成長を神さまに感謝し、これからのさらなる健康を祈ります。
七五三には欠かせない千歳飴は、子供の末永く健やかな成長を願って細く長く、紅白の色で作られ、袋には鶴亀・松竹梅などの縁起物が描かれています。

Q.身内が亡くなりましたが、神社へのお参りはどうしたらいいのですか?
身内の方が亡くなったときは、一定の期間は故人を弔らうことに専念します。その期間が「忌」の期間です。
具体的な期間と例は次の通りです。一般的なものをご紹介しましたので、その地域の習慣を踏まえて、ご参考にしてください。
- 配偶者側の服忌は1親等下げるものとする
- 7歳未満の子供は服忌なし
- 表にない者は服忌なし
- 日数は死亡日から数えはじめる
- 神棚の白紙は死者を出した家のみ掲げる
- その1、 同居の家族が死亡したときに、神棚はどうするか。
- 家族が死亡したことを神棚にお祀りしている神様に奉告し、神棚の前に白い紙を貼ってください。その他、病気平癒を祈願した神社があれば、代理の方に参拝してもらって神様に奉告するか、又は遥拝して祈願を解いてください。神棚の前に貼った白い紙は50日祭又は49日の法要の後に取り、普通のおまつりの仕方にもどってください。
- その2、 服喪期間を過ぎて神社参拝を再開するタイミング
- 神社参拝は「忌」の期間を経過すると再開しても差し支えありません。しかし、同居の家族の場合には50日祭又は49日の法要を過ぎてから神社参拝を行う方が良いでしょう。忌の期間は、本来であれば歌舞音曲を避けて、宴会などに参加せず、故人の弔いに専念する期間とされるので、神社にも参拝しなかったものです。
| 死去された方 | 忌 | 服 | |
|---|---|---|---|
| 1親等 | 父・母・子・夫・妻 | 50日 | 1年 |
| 2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 30日 | 150日 |
| 3親等 | 曽祖父母・伯父叔母・甥姪・曽孫 | 10日 | 30日 |
| 4親等 | 従兄弟姉妹 | 3日 | 7日 |
Q.岡山県には神社が何社あるのですか?
現在は岡山県神社庁と関係のある神社が1610社ありますが、これは宗教法人になっていて神社本庁に包括されている神社の数です。
昭和16年には岡山県庁に登録されていた神社が約5000社ありましたので、現在も他の宗派の神社や宗教法人以外の神社を合わせるとその数はもっとたくさんあると思います。
Q.地区でお祀りしている荒神様があります。境内に大木が数本ありまして、その落ち葉の清掃に難儀しております。相談の結果、その枝葉を切り落とそうと言う事になりましたが、神社の樹木はむやみに切ったりするもではないと言われますがどのようにしたら良いでしょうか。
神道は元々自然崇拝から成立したものです。古代の人々は「万物神あり」と称して、全てのものには神が宿ると考えていました。
特に大木や岩、滝、山、海などは神様の依代(ヨリシロ)として畏敬の念を持っていました。即ち、大木などには神様が宿っており、木そのものが神社と同じように崇拝の対象となっているのです。木の神様は久々能智神(くくのちのかみ)という神様で、森を作り、水を蓄え、酸素を作り出してくれる生命の源となる神様です。私たちはこの神様によって生かされており、常に感謝の気持ちを忘れてはなりません。しかし、生活する上においては、その木を切ることも致し方ないことですが、大木をもとから切る事は相当な事情が有る場合の他は慎むべきでしょう。枝葉に関しては精気を失わせないように気を付けて切れば良いでしょう。何れにしても、木の神様にその事をお詫びを申し上げ、作業に当たる人に怪我のないように、神職にお願いして伐採奉告清祓のお祭を行って下さい。
Q.巫女さんになりたいのですがどの様にしたらなれるのですか。
神社の巫女になるためには、神職階位のような資格は特に必要がありません。神前での作法や巫女舞、神道や神社に関する知識全般については、それぞれ奉務先の神社において教育しています。しかし、神職を補助して神社奉仕を行うためのしっかりとした心構えが必要になり、勿論、心身共に清浄であり、未婚であることは基本的な条件です。
神社によっては、お正月や祭礼の際に巫女を募集する場合がありますので、それぞれの条件に応じて神社に問い合わせて下さい。その際には、くれぐれも神様に奉仕をするという気持ちを忘れないで下さい。