葦守八幡宮
アシモリハチマングウ
由緒
当宮は世にいう葉田葦守宮で応神天皇行幸の旧跡である。葉田葦守は応神天皇の皇妃吉備兄媛の郷里であり、応神天皇の22年9月この地に御臨幸になった。
応神天皇はこの行幸において、兄媛命の兄御友別命及びその子、兄弟のもてなしを受けたことを大変喜ばれ、吉備の地を分国し、長子の稲速分(下道臣の祖)に川嶋県、次子仲彦(上道、香屋臣の祖)に上道県、末子弟彦(三野臣の祖)に三野県、兄の浦凝別(苑臣の祖)に苑県、弟の鴨別(笠臣の祖)に波区芸県を与えられた。
このように当宮は吉備の国の建国にゆかりのある宮である。天皇崩御の後、御友別命の子中津彦命(仲彦)は、天皇の仁徳を追慕し、天皇の神霊をその行宮跡に斎き祀り、葉田葦守宮と称したのが現葦守八幡宮である。
爾来中津彦命の子孫で、葦守に居を構えた香屋臣(賀陽氏)は、一族中から相つぎ神主を送り出し足利氏末年に至るまで連綿と奉仕した。
葦守八幡宮は代々の守、介や武将からも崇められたが、中でも豊臣秀頼は慶長12年奉行小出大和守をもって神鏡一面を奉納され、豊臣家再興を祈願している。
平安時代末期の嘉応元年(1169)につくられた足守荘園図には庄の中央から少し北寄りの現葦守八幡宮の地に、八満山と八幡宮の文字が見え、社と鳥居が図示され鎮守の神として庄の信仰の中心になっていた当時の様子がうかがえる。
慶長年中従三位木下家定がこの地に移封後約250年間は同家累代藩主の産土神として、また領内総鎮守として、格別尊崇され、社殿の修理、祭典その他の費用に至るまで寄進された。

日本最古の石鳥居
葦守八幡宮・岡山市
基本情報
| 神社コード | 10066 |
|---|---|
| 神社名 | 葦守八幡宮(アシモリハチマングウ) |
| 通称名 | |
| 旧社格 | 郷社 |
| 鎮座地 | 〒701-1464 岡山市北区下足守468 |
| 電話番号 | 086-295-1770 |
| FAX番号 | |
| 駐車場 | 有 10台 |
| 御祭神 | 応神天皇,神功皇后,玉依媛命,兄媛命,御友別命 |
|---|---|
| 御神徳 | |
| 主な祭典 | 1月1日:歳旦祭 7月第4日曜日:大祓祭 10月第2日曜日:秋季大祭 |
| 宮司宅電話 | 086-295-0057 |
| URL | |
| 特記事項 |
- 交通アクセス
- JR吉備線足守駅から北へ4km
- 氏子地域
- 岡山市北区(下足守、上土田、足守)
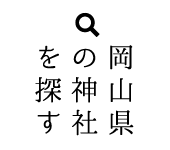












葦守八幡宮の表参道競馬場先に建立されている石鳥居は、両部石鳥居としては日本最古1361年であり、国重要文化財に指定されている。