田井八幡宮
タイハチマングウ
由緒
当社は、玉野市田井尾上、十禅寺山南麓の内海を眼下に見渡せる静寂な地に鎮座し、田井・築港一円を氏子としている。元々田井地区は早くから開けた土地で、古くから神社があったといわれているが、創立年代は不詳。御神徳は『厄除』とされている。
室町時代の田井の豪族、田井新左衛門信高(南北朝時代)の後裔佐々木筑前守久信が3度も夢で八幡様からのお告げを受け、この地に宇佐八幡宮から御分霊を勧請して神社を再建し神像を奉納した。本殿内部に文正元年(1466)丙戌11月15日願主佐々木筑前守源久信の墨書銘が有る神像を安置し、一族の繁栄と地域の発展を祈願したと伝えられている。
その後、棟札によると寛文元年(1661)に本殿が改築され、続いて元禄12年(1699)幣殿、拝殿、釣殿が改築された。
本殿は万延元年(1860)に入母屋造り檜皮葺きに改築、昭和61年(1986)銅版葺きに改築され、現在に至っている。
拝殿は明治32年(1899)に建立され、その後内部の補修が行なわれている。
随神門は明治18年(1885)の建立で、屋根瓦の補修が行われているものの、当時のままの状態が保たれている。
本殿や幣殿、拝殿の廻りは大小様々な木々に囲まれ、荘厳な雰囲気が漂い、拝殿東には根回り約6メートル、樹齢700年と推定される樟樹(くすのき)がそびえ立ち、御神木とされ、天然記念物に価すると言われている。
平成13年7月、拝殿斜め前に社務所が完成した。
正月・節分・輪くぐり・大祭・七五三等の祭礼には参拝者も多く賑やかで、とりわけ、子供達が団体でお詣りする「節分祭」は、田井地区の風物詩にもなっている。
くすの木が地元の新聞や県の広報紙にも掲載され、遠方からのお詣りの方も見られるようになった。また、十禅寺連峰へのハイキングコース入口付近でもあり、神社に参拝してハイキングに出発される方も多い。

700年の楠の木
田井八幡宮・玉野市
基本情報
| 神社コード | 04011 |
|---|---|
| 神社名 | 田井八幡宮(タイハチマングウ) |
| 通称名 | 田井八幡宮 |
| 旧社格 | 村社 |
| 鎮座地 | 〒706-0001 玉野市田井5-12-30 |
| 電話番号 | 0863-31-2335 |
| FAX番号 | 0863-31-2395 |
| 駐車場 | 有 10台 |
| 御祭神 | 応神天皇,仲哀天皇,神功皇后,品陀和氣命 |
|---|---|
| 御神徳 | 厄除け |
| 主な祭典 | 10月第2土日曜日:例祭 |
| 宮司宅電話 | |
| URL | |
| 特記事項 |
- 交通アクセス
- JR宇野線田井駅下車 東へ徒歩10分両備バス 田井バス停 東へ徒歩約9分
- 氏子地域
- 玉野市(築港1丁目、築港2丁目、築港3丁目、築港4丁目、築港5丁目、田井1丁目、田井2丁目、田井3丁目、田井4丁目、田井5丁目、田井6丁目)
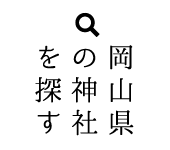












田井八幡宮(玉野市田井)拝殿東側に一株の樟樹がそびえ立っている。目通り周囲は4.3メートルにもおよび、700年を経ているとみられる巨樹である。
当神社草創に関わるものと推察され、御神木で天然記念物に値すると云われている。(玉野史跡社寺案内から)
古くから田井地区一円を見下ろし、人々の暮らしぶりを眺めてきたものである。