稲荷神社
イナリジンジャ
由緒
当社は岡山県倉敷市茶屋町に鎮座する稲荷神社である。社伝によれば、江戸時代中期の享保19年(1734)6月に京都の稲荷神社(現在の伏見稲荷大社)の御分霊を勧請して鎮座した。その前身には、領主戸川公の寄進地(現在の鎮座地)に「早島村城山正一位稲荷大明神」の御分霊を勧請していた。創建時期は不明だが、宝永4年(1707)帯江沖新田村干拓完成直後の事と伝えられ、参道石鳥居に「正一位稲荷大明神」の額が残り、往時を物語る。
鎮座の前年である享保18年(1733)に本殿が造営された。造営の際は、村内在住の大工のみでは人手が足らず、塩飽諸島の本島から大工を招き造営に当たったとの記録が残っている。この本殿造営に際して奉製された棟札は現存しており、そこには、国が穏やかに治まり、氏子が繁栄することを願い「國家靜謐 氏子繁栄」と記されている。その後の安永3年(1774)、本殿を境内東南に移築し、旧本殿跡地に再び本殿を造営した。
江戸時代は法輪寺の僧侶が祭祀に当たっていたが、明治5年の神仏分離に伴い、社名を「稲荷宮」から現社名である「稲荷神社」に改称し、御祭神を三柱とした。大正3年9月24日に神饌幣帛料供進神社に指定された。
近代に入り、港町から駅前町として、或いは産業の町として栄えたため、水田は次第に減少し、住宅地が多数を占めるようになったが、現在でも組合ごとに「春祈祷」(はるぎとう)と呼ばれる神事を行っている。令和16年(2034)には御鎮座三百年という記念すべき年を迎える。

浦安の舞
稲荷神社

稲荷神社・夏越祭
稲荷神社・倉敷市
当社の夏越祭では、伝統的に神聖な植物とされている真菰(まこも)を用いて「茅の輪」を奉製する。7月最終日曜日を祭日として斎行する「夏越祭」では、責任役員、総代、参列者が宮司の先導に続いて輪くぐりを行う。

稲荷神社・春季大祭
稲荷神社・倉敷市
春季大祭における責任役員、総代奉仕による献饌・手長奉仕。当社では、羽織・浅黄袴を着用した責任役員、総代が神饌伝供の手長を奉仕する。

稲荷神社・秋季大祭
稲荷神社・倉敷市
一日かけて町内を巡幸する「神幸祭」を終え境内にて記念撮影。御神幸の行列には、責任役員総代、神輿所役に加え、茶屋町の鬼が随行。加えて、小学生男子の五色幣所役、小学生女子の舞姫も行列に加わる。
基本情報
| 神社コード | 02059 |
|---|---|
| 神社名 | 稲荷神社(イナリジンジャ) |
| 通称名 | 茶屋町稲荷神社 |
| 旧社格 | 村社 |
| 鎮座地 | 〒710-1101 倉敷市茶屋町1547 |
| 電話番号 | 086-428-5577 |
| FAX番号 | 086-428-5577 |
| 駐車場 | 有 8台 |
| 御祭神 | 宇迦之御魂神,須佐之男命,神大市比賣命 |
|---|---|
| 御神徳 | 五穀豊穣, 商売繁昌, 厄除開運, 無病息災, 開運招福, 安産 |
| 主な祭典 | 2月初午:初午祭 5月第2土曜日・翌日曜日:宵宮祭・祈年祭(春季大祭) 7月最終日曜:夏越祭 10月第2土曜日・翌日曜日:例祭・神幸祭(秋季大祭) 11月23日:新嘗祭 |
| 宮司宅電話 | |
| URL | https://inari-jinja.com/ |
| 特記事項 | 宮司在社時間9:00~16:00(火曜日休社) ・授与所受付:9:00~16:00 ・祈願受付:9:00~15:00 |
- 交通アクセス
- JR瀬戸大橋線・宇野線茶屋町駅から北東へ600m
- 氏子地域
- 倉敷市(茶屋町)
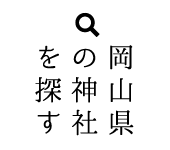


















当社の秋季大祭では、町内から選出された小学生児童による「浦安の舞」が奉納される。例祭時は神前舞として、例祭後は神賑行事として行われる。