厄神社
ヤクジンジャ
由緒
当神社は、神速須佐之男命を奉斎し、56代清和天皇の貞観9年(867平安前期)8月備後の国鞆之津祇園宮から小林庄都羅之郷、宮之壇(現宮之浦)に勧請「薬神宮」と称した。
その後土地開発により住民が連島山脈の南面に移住すると、第99代後亀山天皇の天授3年(1378南北朝)春日北朝の永和3年春日字小船(現西之浦)の地に奉遷し、「疫神宮」と改称した。
第101代称光天皇の応永23年(1416室町中期)11月13日字小川(西之浦)の地に遷し奉り、又第104代後柏原天皇の大永8年(1529室町後期)5月吉日古宮(現西浦小学校東端)に遷宮した。再び第107代後陽成天皇の慶長12年(1607幕末)の秋、願主物部氏、船氏、生和氏等協力して御本殿を建立した。
第111代東山天皇の宝永6年(1709江戸中期)9月7日現地当山の石山に奉遷し、「厄神宮」と称した。
明治7年神仏分離により「厄神社」と改称する。当山遷座後、大正10年奉遷200年祭、昭和46年5月奉遷250年祭を執行現在に至る。
往古よりあらゆる災難防護、病気平癒、産業繁栄、文芸、学問の神として知られており、その御神徳を仰ぎつつ、更に現在では厄除祈願、安全祈願等が盛んに行われている。また多くの会社企業等から業務の安全、繁栄を祈り広く崇敬されている。

神輿渡御
厄神社・倉敷市

神社の夕暮れ
厄神社・倉敷市
美しい夕日が沈む境内。

鳥居と彼岸桜
厄神社・倉敷市
3月になると境内に植えられた彼岸桜が開花する。

七五三
厄神社・倉敷市
境内から眼下の風景を見下ろす七五三詣りの子供。

新年の参道
厄神社・倉敷市
厄神社のご祭神は神速須佐之男命で、記紀神話で出雲系神統の祖とされる神。伊弉諾・伊弉冉二尊の子。天照大神の弟。粗野な性格から天の石屋戸の事件を起こしたため根の国に追放されたが,途中,出雲国で八岐大蛇を退治して奇稲田姫を救い,大蛇の尾から天叢雲剣を得て天照大神に献じた。新羅に渡って金・銀・木材を持ち帰り,また植林を伝えたともいわれる。「出雲国風土記」では温和な農耕神とされる。
基本情報
| 神社コード | 02043 |
|---|---|
| 神社名 | 厄神社(ヤクジンジャ) |
| 通称名 | やくじんさま |
| 旧社格 | 村社 |
| 鎮座地 | 〒712-8001 倉敷市連島町西之浦3815 |
| 電話番号 | 086-444-7372 |
| FAX番号 | |
| 駐車場 | 有 10台 |
| 御祭神 | 神速須佐之男命 |
|---|---|
| 御神徳 | 厄除け, 安全祈願 |
| 主な祭典 | 5月15日に近い日曜日:春祭 7月夏休み最初の日曜日:夏越大祓祭 10月16・17日(第2日曜日の土日):秋季例大祭 |
| 宮司宅電話 | |
| URL | |
| 特記事項 | 境内に近代詩人、薄田泣菫の詩碑有り |
- 交通アクセス
- 倉敷駅から水島方面10km、バスで30分 新倉敷駅から連島方面へ7km バスで20分
- 氏子地域
- 倉敷市(連島町西之浦、水島海岸通、水島中通、水島西通、水島川崎通)
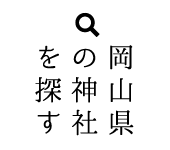
















厄神社の秋祭りは、江戸時代の後期に、現在の倉敷市連島町西之浦へ本殿が移された際に、御神輿の巡行に御供をする千歳楽が作られたことに始まると言われています。
300年の歴史をもつ秋祭りでは、氏子町内の西町、奥、四丁内、腕の4つの支部からそれぞれ大若・小若と呼ばれる大小合わせて8基の千歳楽が繰り出し2日間で西之浦地区を15キロから20キロ曳行します。祭り初日は午後3時半に猿田毘古神社わきの串ノ山公園に8基の千歳楽が集結し、太鼓を叩き、伊勢音頭をアレンジした連島小唄を歌いながら力強く担ぎ上げ、秋祭りを盛り上げていました。