箆取神社
ヘラトリジンジャ
由緒
当社の創建年代は不詳であるが、伝説によれば往古連島は都羅之郷と称し一孤島であり、第40代天武天皇の御代にあった壬申の乱の頃、鎮座地前面の海上に箆の御神紋が顕れた事に因り、箆取大権現と称した。
また、江戸時代の宝暦年間におては、当地七浦の総鎮守として信仰の中心となり、霊験著しく神恩に浴する者遠近に及び殊に成羽藩主山崎主*之助並に地方権勢家の崇敬厚く、75社の御眷族(神使)を俗謡にまで唱へられ、尊信する人は遠近に及び霊徳顕著となった。
神社は隆昌を極め、境内は広大で社殿もまた稀有な宮造りと県下一の廻廊を左右に巡らし、境内境外には桜、楓、ツツジが数百本植裁されている。四季の眺めは変化があり、又絵馬殿からの眺めは水島灘の風光並びに水島工業地帯の展望台として信仰と観光を兼ねた県下稀に見る神社である。
(注)文中の*は、「衣」偏に「ソ」をしてその下に「兄」である。

桜と社殿
箆取神社・倉敷市

境内の桜
箆取神社・倉敷市
桜の季節にはピンクのトンネルができ、遠方に水島灘と高梁川が臨める。

新年を待つ社殿
箆取神社・倉敷市
箆取神社は水島地域西部の連島町大平山の中腹にある神社である。
創建年代は不詳であるが、連島は奈良時代には都羅之郷と称し、壬生の乱の神官が神社から南に広がる瀬戸内海を眺めていた時、海面に 「箆」の神紋が顕れたことから箆取大権現と称したといわれている。江戸時代初期までは、連島は瀬戸内海に浮かぶ狐島で、都から九州の太宰府を結ぶ海路で重要な位置を占めていたことにより海にまつわる伝承が多い。また、宝暦の頃には連島の総鎮守として信仰集め、広い境内には長い回廊が左右に巡らされている。
周辺には桜、楓、ツツジが数百本植栽され、四季の変化が楽しめ、絵馬殿からの眺めは手前から西之浦の旧市街、水島市街と水島臨海工業地帯、遠方に水島灘と高梁川が臨める観光地となっている。なお、当社は崇敬神社につき氏子を持たない。

干支押し絵絵馬
箆取神社・倉敷市
箆取神社(倉敷市連島町西之浦)では毎年新年拝殿外壁にその年の干支をモチーフにした巨大「押し絵絵馬」を掲げている。押し絵は、縦1.5メートル、横1.8メートルで、まず構図をもとにベニヤ板で型を作り、そこにパッチワークなどで使用するアクリル綿をのせて縮緬布でくるみ、絵馬型の土台の板にボンドで貼り付けている。
基本情報
| 神社コード | 02042 |
|---|---|
| 神社名 | 箆取神社(ヘラトリジンジャ) |
| 通称名 | |
| 旧社格 | 無格社 |
| 鎮座地 | 〒712-8001 倉敷市連島町西之浦3184 |
| 電話番号 | 086-444-8223 |
| FAX番号 | 086-448-0980 |
| 駐車場 | 有 30台 |
| 御祭神 | 大綿津見神,豐玉姫命,玉依姫命 |
|---|---|
| 御神徳 | 火難除け, 盗難除け |
| 主な祭典 | 4月第1又は第2日曜日:桜祭り 1月6日:寒入り大祭 旧暦6月15日:夏大祭 |
| 宮司宅電話 | 086-444-8223 |
| URL | |
| 特記事項 | 寒入り大祭の日に参詣すれば1年間火事盗難にあわないと伝えられている。 |
- 交通アクセス
- 箆取神社バス停から約500m
- 氏子地域
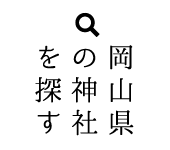




















社殿に桜が映える。