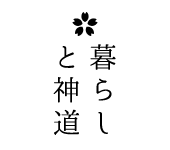神事の紹介
千度踏恩徳感謝祭
瀧神社
708-1300 勝田郡奈義町滝本1973
- 祭礼日時
- 4月第3日曜 瀧神社遥拝所での春祭りの後、「代官塚」に移動
- 文化財指定
- 無
江戸時代、当地区が天領だったころ、天災(早魃・広度風・洪水)が続き、土地が荒廃し、農民は大層疲弊し困窮していた。その窮状を察した「池田仙九良」「重田又兵衛」代官は、年貢の減免や使役の軽減などを幕府に申し出て民を救済した。文化12年(1715)、当地の庄屋と百姓は2人の代官の名前を刻んだ石碑を建立し、恩徳の碑として感謝の意を後世に残した。また、昔旧暦3月18日に村人総出でその年の豊作を祈って、東の天王社と西の仮社(現在は合祀されて跡がない)、との間を千度行き交う行事があった。榊の葉を一枚ちぎって御神前に供えることにより、お参りの回数を数えた。現在では、瀧神社遥拝所での春祭り神事後、役の行者像(修験道の祖~当地は明治初年まで山岳信仰の霊地で修験者が多くいた)のお祭りされている場所に移動し、そこでは線香を供えて豊作を祈り、仏式の拝礼をする。その後、代官塚に移動して恩徳感謝祭を行う。この祭典では、古式に則り、参列者が榊の葉をちぎってお供えする儀礼がある。
神事の分類
神事の詳細
| 祭りの時間帯 |
|
|
| 祭りの対象 |
|
|
| 祭祀規程上の区分 |
|
|
| 祭りの趣旨・由来 |
|
|
| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |
|
| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |
|
|
| 祭典の参列者数 |
|
|
| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |
|
|
| 神職以外の祭りの奉仕者 |
|
|
| 神饌・供え物 | 品目 |
- |
| 供え方 |
- |
|
| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |
- |
|
| 競技・演武等の行事 |
- |
|
| 芸能 |
- |
|
| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |
- |
|
| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |
呼称 |
- |
| 形態 |
- |
|
| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |
- |
|
| 行列・社参・参列 | 形態 |
- |
| 一般の参列の可否 |
|
|
| その他の行事・所作 |
- |
|
祭りの時間帯
- 午前
祭りの対象
- 神社の祭神以外の神々(舟霊・山神・風神などの祭りなど)
- 祖霊・英霊・その他諸々の神霊(慰霊祭・祖霊祭・祖霊社祭・忠魂碑・顕彰碑・供養碑や墓前の祭りなど、大祓・遥拝もこれに含む)
祭祀規程上の区分
- その他の諸祭(特に規程による区分のされない祭りを含む
祭りの趣旨・由来
- 歴史上の事件や人物に由来する祭り
祭りの規模
祭典奉仕の神職数
- 1名
祭典奉仕の神職以外の祭員数
- なし
祭典の参列者数
- 30名前後まで
祭礼行事の神職・祭員以外の所役
- 10名以上
神職以外の祭りの奉仕者
- 総代(全員または代表・有志・選抜者)
- 町内会・自治会の役員
神饌・供え物
品目
-
供え方
-
芸術・文芸・物品奉納供進等の行事
-
競技・演武等の行事
-
芸能
-
こもり・禁忌・禊祓・神占などについて
-
ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて
呼称
-
形態
-
神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御
-
行列・社参・参列
形態
-
一般の参列の可否
- 氏子または崇敬者のみ参列・参加が可
その他の行事・所作
-