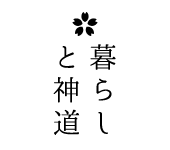神事の紹介
初卯祭
本荘八幡宮
711-0933 倉敷市児島通生22
- 祭礼日時
- 文化財指定
- 無
古くより当神社の初卯祭は春の準例祭として斎行されて来たが、旧暦2月の初の卯の日は寒いので、2・3年前から、彼岸前の土・日に変更している。具体的な神事内容は別紙「日待祭」に記述の通りであるが、宵宮に参列した通生奥部落のメンバーが、神前に飾り、お祓い済みの天狗面(鼻高)3面と衣装、獅子頭の付いた衣装一組。更に新しい5色の御幣3本を持ち帰り、翌日獅子舞と、天狗面に衣装を着け、青笹を持って氏子地域を清祓いし、賑わして廻る慣例となつている。伝えられるところによると、今から凡600年ほど前、この地域が激しい飢餓に見舞われた際、住民が神前に天狗面・獅子面を献じ、神楽舞を奉納して祈願したのが始まりとされ、2月の初の卯の日の前日にお日待ちをし、翌朝早々より村内を巡回したことが慣わしとなった。昭和56年に、奥部落有志が保存会を作り、天狗面・獅子頭・衣装などの修復に取りかかったが、平成26年通生奥育友会をメンバー30名ほどで結成し、単に初卯祭に於ける伝統行事の保存のみではなく、地区全体の活性化と共同体意識を高めることを念願としている。倉敷市重要文化財に指定されている獅子頭1面が現存していて、制作年代不詳ではあるが、かなり昔からの伝統行事であることは疑いないと思われる。
神事の分類
神事の詳細
| 祭りの時間帯 |
|
|
| 祭りの対象 |
|
|
| 祭祀規程上の区分 |
|
|
| 祭りの趣旨・由来 |
|
|
| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |
|
| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |
|
|
| 祭典の参列者数 |
|
|
| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |
|
|
| 神職以外の祭りの奉仕者 |
|
|
| 神饌・供え物 | 品目 |
- |
| 供え方 |
- |
|
| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |
- |
|
| 競技・演武等の行事 |
- |
|
| 芸能 |
- |
|
| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |
- |
|
| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |
呼称 |
- |
| 形態 |
- |
|
| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |
- |
|
| 行列・社参・参列 | 形態 |
- |
| 一般の参列の可否 |
- |
|
| その他の行事・所作 |
|
|
祭りの時間帯
- 午前
- 昼
- 午後
祭りの対象
- 本社(本殿)奉斎の祭神
祭祀規程上の区分
- 例祭以外の大祭
祭りの趣旨・由来
- 皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念する恒例の祭り
祭りの規模
祭典奉仕の神職数
- 1名
祭典奉仕の神職以外の祭員数
- なし
祭典の参列者数
- 30名前後まで
祭礼行事の神職・祭員以外の所役
- 11~100名
神職以外の祭りの奉仕者
- 総代(全員または代表・有志・選抜者)
神饌・供え物
品目
-
供え方
-
芸術・文芸・物品奉納供進等の行事
-
競技・演武等の行事
-
芸能
-
こもり・禁忌・禊祓・神占などについて
-
ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて
呼称
-
形態
-
神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御
-
行列・社参・参列
形態
-
一般の参列の可否
-
その他の行事・所作
- 「鬼」などの仮面が登場する