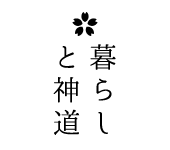神事の紹介
御田植
吉備津彦神社
701-1211 岡山市北区一宮1043
- 祭礼日時
- 8月2日
- 文化財指定
- 県
五穀豊穣を祈願するお祭りで、8月2日夕刻の「厄神祭(茅の輪くぐり)」に始まり「本殿祭」「御斗代祭」よく3日の「本殿祭」「御幡奉納祭」を持って、一連の神事が終了します。両日中に本殿祭では、小・中学生のは早乙女により田舞が奉納されます。実際近年寺社の御田植え祭は夏祭り(御田植え祭協賛行事)実行ん委員会が組織され地域の夏祭りとなっております。特に8月2日の夜が最も賑わしく、たくさんの方が参って来られます。多くの露店が並び、花火も打ち上げられます。当社御田植え祭は、その発祥については不詳であるが、南北朝時祭にはすでに行われておりました。昭和53年に岡山県指定無形文化財になりましたが、時代とともに祭が変遷してきております。
神事の分類
神事の詳細
| 祭りの時間帯 |
|
|
| 祭りの対象 |
|
|
| 祭祀規程上の区分 |
|
|
| 祭りの趣旨・由来 |
|
|
| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |
|
| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |
|
|
| 祭典の参列者数 |
|
|
| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |
|
|
| 神職以外の祭りの奉仕者 |
|
|
| 神饌・供え物 | 品目 |
- |
| 供え方 |
- |
|
| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |
- |
|
| 競技・演武等の行事 |
- |
|
| 芸能 |
|
|
| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |
- |
|
| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |
呼称 |
|
| 形態 |
|
|
| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |
- |
|
| 行列・社参・参列 | 形態 |
- |
| 一般の参列の可否 |
- |
|
| その他の行事・所作 |
- |
|
祭りの時間帯
- 夕刻
- 宵(夕刻から夜)
- 数日間
祭りの対象
- 本社(本殿)奉斎の祭神
- 境内神社の祭神
祭祀規程上の区分
- 例祭以外の大祭
祭りの趣旨・由来
- 皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念する恒例の祭り
- 農耕に関わる由緒や伝承がある祭り(御田植祭など)
祭りの規模
祭典奉仕の神職数
- 6~10名
祭典奉仕の神職以外の祭員数
- 11名以上
祭典の参列者数
- 50名前後まで
祭礼行事の神職・祭員以外の所役
- 11~100名
神職以外の祭りの奉仕者
- 伶人(神職が伶人を務める場合を含む)*伶人とは、雅楽をおこなうもの
- 巫女(神社雇員のほか、臨時の巫女も含む)
- 総代(全員または代表・有志・選抜者)
- その他
神饌・供え物
品目
-
供え方
-
芸術・文芸・物品奉納供進等の行事
-
競技・演武等の行事
-
芸能
- 田遊び・田楽(古典的な田植え歌や田植え踊りなどを含む)
こもり・禁忌・禊祓・神占などについて
-
ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて
呼称
- その他の名称で呼ばれる
形態
- その他、独自な形態や演技・行事をする山車・屋台・ダンジリの類がある
神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御
-
行列・社参・参列
形態
-
一般の参列の可否
-
その他の行事・所作
-