神社ギャラリー
神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。
※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。
神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

カキツバタの群生
菅原神社・笠岡市
境内の御手洗池で5月になると名物のカキツバタ千株が紫色の花を付け、笠岡市文化財に指定されている眼鏡橋を背景に咲き誇る様は源氏絵巻の様相を呈する。

桜と瀬戸内海
新庄八幡宮・倉敷市
境内から桜越しに瀬戸内海が一望できる。遠くに大槌島や香川県が見渡せ往来の船舶の眺めが美しい。

真紅のツツジ
國鉾神社・早島町
神社の一帯に植えられた真紅のツツジは希少であり、近郊からの見物人で賑わう。白、紫の藤棚からの眺めが特に美しい。

洞窟
穴門山神社・高梁市
崇神天皇から、天照大神のご神体である御鏡を、「何処へおまつりしたらよいかさがしてきなさい」という命を受けた豐鋤入姫命が、紀伊国奈久佐浜宮から備中国名方浜宮(現在の穴門山神社)へ奉遷し、4年間奉斎したと伝えられている洞窟。

大鳥居
北山神社・久米南町
神社の鎮座する山王寺山の頂きには、高さ約20メートル、柱の直径約1.5メートルの大鳥居が、神社の森厳さを加へて聳え立ち、遠近の目印となっている。
鳥居の手前はたばこ畑が広がり鳥居とのコントラストが美しい。

日本一の石鳥居
茅部神社・真庭市
安政7年正月、茅部神社の氏子石賀理左文、友金宇平は近江の多賀大社に参拝したとき、同神社の石鳥居が日本一だと聞き、これより大きいものを地元に造り日本一にしようと考え、実測して帰った。
3年後の文久3年にその願いを果たしたという。石材は茅部神社のある岩倉山の花崗岩である。石工は、伯耆国倉吉の横山直三郎、郷原在住の米倉鉄造の2人が腕を振るった。
2本の柱と笠木・島木・貫・額束で組み立てた神明型鳥居で、柱は地中に基礎を作って下部を深く埋め地上の長さ11.45メートル、直径1.20メートル、下部約3メートルを別石で12角に仕上げ、その上に円柱を継ぎ接合点は鉄の鎗でとめてある。地上から笠木の上端までの全高13.8メートルであったが、何度かの補修で下部を埋めたため現在10.65メートルとなっている。

御供
志呂神社・岡山市
通称「京尾御供」と呼ばれ、10月20日に行われる秋祭りに,久米南町京尾の氏子から備えられる神饌行事である。だんごでつくった「ブト」「マガリ」と称する男女の陰と陽を形どったもの3個と、餅でつくった「丁銀」3個、それに米飯1盛、柚子1個、箸1膳、榊葉若干を三宝に盛った7台の熟饌が調整され、御幣を立てた唐櫃にかつがれて供饌される。その製法と形態は、今も厳重なしきたりで行われており、往古の暮らしや物の考え方がうかがわれる貴重な民俗文化財である。

おいつき祭
御前神社・新見市
「おいつき祭」は旧暦3月1日に行われる。神社で祭典の後、清事代(子供)が御幣、絵馬を左肩に担ぎ、おいつき小屋(当番組で茅、稲藁等で作った小社)に安置して、毎月旧暦1日に月次祭を行う。
旧暦11月1日の前日、頭屋にオハケ(約2メートルの高さに束ねたカヤに御幣を付け3束立て、注連縄を張ったもの)を立てる。オハケの中央には、先端に3体の御幣をつけた15~16メートルの真竹を立て、おいつき小屋から清事代により、御幣、絵馬が頭屋の神床に迎えられる。
11月1日になると清事代は頭屋から主人に付き添われ御幣、絵馬を左肩に担ぎ神社に向かい納める。この時膳組を作り神前にお供えし、祭典を行う。祭典が終わると当番組、総代等が膳組を食す。
膳組は団子の吸い物、甘酒、団子粉で作ったちくわ・かまぼこ、よりぎょう(円錐形のおむすび)、干し柿、小餅である。

渡り拍子
諏訪神社・高梁市
当社の渡り拍子は11月第2日曜日の秋祭に行われる。華やかな衣装をまとって、鐘と太鼓の拍子に合わせて神幸祭の行列に加わる。

しゃくし祭り
木野山神社・高梁市
当社の夏季大祭(7月10~16日)の最終日に当たる16日午後に神賑行事として、「しゃくし撒き」が行われる。この行事のため夏祭を「しゃくし祭」と呼ぶ人もいる。
大正時代から行われている「しゃくし撒き」は「災いをメシ(飯)取り福をすくう」という意味で御福の景品が当たる福しゃくしをまぜて約2000本のしゃくしを多数の参拝者に撒いており名物の伝統行事となっている。

七十五膳据え
吉備津神社・岡山市
「七十五膳据え」は春季大祭(5月第2日曜日)と秋季大祭(10月第2日曜日)に行われる。この祭は神社にとっては最も大切な神事であった。現在は前日に、長い廻廊の端にある御供殿という建物に数人の世話人が集まって七十五の神膳を作る。膳の形は御掛盤や平膳や高杯や瓶子など、いろいろの種類があるがそれぞれの膳には白米または玄米を蒸して円塔形の型にはめて作った「御盛相(おもっそう)」と称する飯が中心に置かれ、鯛やそのほかの魚、昆布、竹の子などの野菜、それに柳の箸がそえてある。
膳はみな黒漆塗で、桐紋のついた立派なものである。御掛盤は二人でこれをささげもってはこぷ。平膳その他は一人で持って運ぷ。膳の前には、武具や小鳥をもつ人びとが行列をする。その行列は警固三人、榊持ち、氏子総代、獅子二頭、猿田彦、鉄砲(男児)、鳥籠持(女子)、弓持、矢持、鉾、大太刀、小太刀、五色の幣、御冠、宮司、御掛盤、高杯、神酒、鏡餅、果物、菓子、絹布、綿布、平膳の順序で百数十人の長い行列がつづく。
行列は御供殿から廻廊を進み、先頭が南随神門につくと、いったん停止する。宮司が随神門の神に対して祝詞を奏上する。それが済むと行列は再び進行し、本殿の前につく。そこで待機中の神職が供奉者が持ち運んできた神膳やそのほかの供物を全部受けとって、つぎつぎと神前にそなえる。ここに宮司が祝詞を奏上し、拝殿で巫子の神楽があって祭事は完了する。この神事は午前11時すぎに始まり午後1時ごろ終わる。まことに優雅にして荘重な神事である。
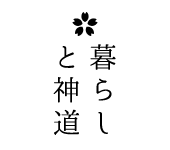



























毎年4月29日午前10時30分から本殿祭を執行し、祭典終了後鳳輦(ホウレン) に御霊を遷し中門に安置する。
鳳輦の前で笛、太鼓の拍子に合わせて2匹の獅子が舞う中、氏子12名が白装束を着け境内の石畳を田に見立てて鍬振りの神事を行う。
五穀豊穣を願う田起こしの神事として同社に古くから伝わっており、当日は多くの参 拝者で賑わう。