神社ギャラリー
神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。
※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。
神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

平安杉
高岡神社・真庭市
高岡神社(真庭市上中津井)の境内入り口に聳える大杉は、根本から少し上がったところから二またに分かれ、それぞれが天に向かって伸びている。
通称「平安杉」の名で親しまれており、幹の周囲8.5m樹齢は同社が創建された年からと考えられ800年とされる。
その他、樹齢百年を超える杉、檜、モミなどの鬱茂する社叢は、岡山県郷土自然保護地域に指定され、本殿は真庭市指定建造物、大杉は真庭市指定天然記念物に指定されている。

供膳祭
鶴崎神社・早島町
この神事は、春・秋の大祭に執り行われる献饌(神様にお供え物を献ずる儀式)である。
吉備津神社や当社ではこの儀式が祭りの中枢を担っている。
供膳は本膳が3台、朱三方が16台、通常の神饌が11台の合計30台を供膳所で調理し、注連縄を張った伝供道を総代、幹事が長い行列をつくり、手渡しにより本殿内に運ぶ。本膳には御盛相(米を蒸し円筒形の竹型にはめて押し抜いたもの)・盛り込み(五種類の野菜)・鯛に箸が一膳副えられる。朱塗りの大三方には、御盛相・小餅・小鯛・果物がそれぞれ盛りつけられる。

700年の楠の木
田井八幡宮・玉野市
田井八幡宮(玉野市田井)拝殿東側に一株の樟樹がそびえ立っている。目通り周囲は4.3メートルにもおよび、700年を経ているとみられる巨樹である。
当神社草創に関わるものと推察され、御神木で天然記念物に値すると云われている。(玉野史跡社寺案内から)
古くから田井地区一円を見下ろし、人々の暮らしぶりを眺めてきたものである。

干支押し絵絵馬
箆取神社・倉敷市
箆取神社(倉敷市連島町西之浦)では毎年新年拝殿外壁にその年の干支をモチーフにした巨大「押し絵絵馬」を掲げている。押し絵は、縦1.5メートル、横1.8メートルで、まず構図をもとにベニヤ板で型を作り、そこにパッチワークなどで使用するアクリル綿をのせて縮緬布でくるみ、絵馬型の土台の板にボンドで貼り付けている。

巨大干支の置物
玉井宮東照宮・岡山市
平成19年秋、造形作家の高島氏に発砲スチロールを造形して、着色を施した「ねずみ」の制作を依頼し、平成20年の元旦からこの年の干支である巨大「ねずみ」を社頭に置いている。一見したところ、大きな備前焼の置物と見間違えるような出来となっており、参拝者は一様に驚くようである。十二支が揃うまで続けられ拝殿に展示されている。

横仙歌舞伎と回り舞台
松神神社・奈義町
横仙(よこぜん)歌舞伎とは江戸時代、諸国をまわる上方歌舞伎の舞に魅せられた人々により、山間の各地で発祥した農村歌舞伎、あ るいは地下(じげ)芝居の一種である。県東北部那岐山麓一帯は古くから横仙地方と呼ばれ、この地方に伝わる農村歌舞伎として伝承されており、岡山県を代表する文化の一つとして昭和51年に県重要無形民俗文化財に再指定されている。
松神神社(勝田郡奈義町中島東)にある舞台(昭和38年に県重要民俗文化財に指定)は、弘化三年(1846)に建築され舞台中央には特殊な木製滑車32個を取り付けた直径五、8メートルの皿廻し式(ろくろ式)の回り舞台が装置してあり、場面転換ができる事が大きな特徴となっており、平成18年に大規模な修復工事が行われ、同年から再び歌舞伎の奉納が復活した。

浮かび干支
由加神社・和気町
社殿裏の山林中腹に10m×8mの櫓を作り、電球を入れた約200灯の提灯でその年の干支を作り闇夜に浮かび上がらせる。
毎年大晦日から1日朝までと1日、2日、3日は夕刻から9時まで点灯。

建国禊ぎ
安仁神社・岡山市
この行事は安仁神社の氏子や崇敬者でつくる安仁神社崇敬会の行事として、平成元年から行われている。
第1代神武天皇が大和の橿原宮(橿原神宮)で即位された我が国の建国記念日に思いを馳せ、祭神の五瀬命(いつせのみこと・神武天皇の皇兄)を祀ることから、この日を記念して、崇敬者が集まり、心身を清め、穢(気枯れ)を消除し、喜びにつけ悲しみにつけ、魂に勇気と精神力を与えるために続けられている。
早朝、有志により行場「宝伝(旧)海水浴場」の海浜を清掃設営の後、神社で祈祷し海浜に出て、褌と鉢巻き姿になり、宮司の先導にて鳥船行事(準備運動)を行い、ご祈願の「神木」を手に手に寒風吹きすさぶ海に肩まで入り大祓詞を奏上しながら、氏子崇敬者の諸願成就を祈る。

粥管祭
森神社・吉備中央町
森神社の粥管祭は江戸時代後期、凶作に苦しんだ農民等が作物の栽培について神宣を求めたのが起源とされる。
神事は境内の鉄鍋をかけ、その中に米や水と共に「早稲」、「晩稲」などの印を付 けた竹筒5本を入れ、約20分煮込んだ後、宮司が竹筒を取り出し神前に奉納する。祝詞奏上後、竹筒を小刀で割り、中の粥の量が多いほどその作物の作柄は良いとされる。(加茂川町重要文化財)

お当まつり
松尾神社・吉備中央町
松尾神社の当屋祭として毎年2月22日に行われる。
氏子区域に上田東と48屋敷があり、この48屋敷の中の本当、次当の両当番、4つの座、8つの座が祭の主役を勤める。
宮司が「氏神様へ御礼申す」の言葉で、当屋行事(宮座行事)が始まる。「四つの座へ御礼申す」、「八つの座へ御礼申す」などに続いて御神楽祭り、御当渡しなどの神事がある。

お田植祭
長田神社・真庭市
毎年5月5日特殊神事としてお田植祭(菖蒲祭)が稲の豊穣と氏子の繁栄(安産) を願って行われる。
拝殿に神饌として産米(ウブゴメ・洗米に煎った黒豆とミョウガの茎を刻んで混ぜる)、スルメ、ウド(山ウドの若芽)、赤飯、寿司、煮しめ等が供えられ、実際の農具をかたどった木製の農具を使用し、牛による荒起こしから鍬代までを忠実に再現する。
神事には「オサン」、「百姓頭」、「田人」の役掌がある。
「オサン」お産役を演ずる役。産米を奉持し、昇殿の途中に懐中から「御子代」(ミコシロ・祭の前夜宮司が秘かに紙で人形を作り、奉書で包んで御子と墨書する。お産の御守)を階段の途中に落とす。この位置によりその年のお産の難易を占う。
「百姓頭」お田植祭の指揮者であり、時には農夫、牛使いを演じる役。
「田人」菖蒲を牛の角に見立てて額に角形に付け、農具を牽く役。
お田植えの準備が終わると、宮司は菖蒲の束を稲苗に見立て、三台の三方に3等分 して置く、中央が中稲、右が早稲、左が晩稲で束の数が最も多いのが豊作と占う。神事終了後、産米と菖蒲は拝殿に置かれ、産米は産婦が、菖蒲は苗代の水口に、牛の角に使った菖蒲は牛舎に掛けて御守とする。

夏祭だし
川合神社・吉備中央町
毎年8月23日の夏祭に催される。 境内に7ヶ所の小屋が設けられ、それに2体又は3体の人形が置かれる。その特色は胴体、腕、手、足はをワラで作り、衣装、着物は色紙をハサミや小刀で裁って糊で張り合わせて着せられる。
古くは疫病の退散と五穀豊穣を祈願するためであったが、長い間には芸術性を加え、 歌舞伎のだし物をつくるようになった。今では氏子、各区青年の手により、一ヶ月近くもかかって作られ、その日は花火も盛大に上げられる。(岡山県重要民俗資料)

ゴザ船形山車
兵主神社・岡山市
毎年、7月14日に近い日曜日の夏祭りに合わせ氏子や阿津芸能保存会の奉仕により、ゴザ船形山車(ダシ)が神社から阿津4地区西原1地区を囃しに合わせ巡幸する。
午後2時30分から祭典。午後3時から遷霊の後境内で山車を練り、急勾配の石段を 下る様は迫力がある。
宮下りした山車は氏子内の御旅所を巡幸し、午後8時ロープで再び石段を引き上げられる。
船形の山車は珍しく、独特な太鼓のリズムと相まって阿津の夏を彩る。

祷屋講
錦織神社・美咲町
祷受人は輪番制(11家)で毎年定められた順序で交代する。祷屋講の当日、神事 が行われ、次の祷受人の補佐としての副精進(ソエショウジン)をくじ引きで決め、 上座に現在と次の祷受人、その横に各々の副精進が座り、その他の講人は適宜に座に つき直会(なおらい)が始まる。
直会は黒い漆塗りの大椀2個に酒を満たし、2人の祷受人が各々一口飲み、その後 左右に廻し、空になるまで続ける。
直会が終わると。次の祷受人が「御神殿」を肩に担ぎ、副精進が赤い幟を持って次 の祷受人の家まで先導する。(その際、後を振り返ってはいけない)祷受人の家に着 くと、庭に木で新しく造った社に「御神殿」を納め幟を立てる。
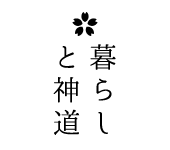


























新見市哲多町成松に鎮座する八幡神社・通称諏訪山八幡神社では、毎年5月5日の子供の日に合わせ、神社で子供祭を執行し、神社から100メートル程離れた川に子供の成長を願って沢山の鯉のぼりを揚げている。
この催しは、昭和63年か始められており、当時は神社の駐車場脇にロープ引いて、50匹程度揚げていたが、周りの樹木が段々と大きくなり、折角揚げた鯉のぼりが見えなくなってきたので、神社の側を流れる本郷川の場所に変更し、現在は、川を渡り100メートルの長さに100匹の鯉のぼりが泳ぐ一大パノラマが広がった。
氏子の人々も毎年5月が来るのを楽しみにしており、噂を聞いて見物に来る人や、通り掛かった人々が珍しさもあって、記念撮影をする人が後を絶たない。