神社ギャラリー
神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。
※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。
神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

湯立て神事
松神神社・奈義町
松神神社(勝田郡奈義町中島東)で行われる「湯立て神事」。日本の伝統的な神楽の形式のひとつ。
釜で湯を煮えたぎらせ、その湯をもちいて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、その年の吉兆を占う神事の総称である。 別名を湯神楽または湯立神楽とも言う。

輪くぐり祭
八幡神社・勝央町
八幡神社(勝田郡勝央町豊久田)の輪くぐり祭に神職に続き総代、氏子が茅の輪をくぐる。
祭りの日に茅を刈って、綺麗なものだけをより分けて境内に大きな輪が作られ、その輪を左、右、左と三回潜り参拝することによって元気に夏が過ごせるよう無病息災を祈願する祭りであり、全国の神社に広まっている。この祭りの故事は備後風土記逸文に記されている。
『素盞嗚命が南海の旅をしていた途中、一夜の宿をある兄弟に頼みました。
裕福な弟の巨旦将来はあっさり断りましたが、貧乏だが心の優しい兄の蘇民将来は素盞嗚尊を快く迎え入れました。
蘇民将来一家の温かいもてなしを大変喜んだ素盞嗚尊は、「疫病が流行れば、茅の輪を作って門に懸けよ」と言い残して旅立ちました。
その後、疫病が大いに流行り、茅の輪を門に懸けた蘇民将来一家は無事助かり、巨旦将来一家は滅んでしまいました。』

火神舞
下見神社・真庭市
下見神社(真庭市下見)では秋の大祭に火神舞(ひのかんまい)が行われる。
真っ赤に燃えるいろりに入れられた33個の餅を男衆が奪い合う独特の伝統行事で、氏子等が無病息災を祈る。
神事に続いて火神舞が始まると、男衆約10人がはちまきを頭に巻き、肩を組んで拝殿内のいろりを囲んだ。「わっしょい、わっしょい」の掛け声とともに輪は左右に回ったり、前後に押し合いへし合い。男衆がしゃがんだのを合図にいろりに餅が放り込まれると、やけども恐れず素手で奪い合った。
火神舞の起源は分からないが、餅を手に入れた人は幸せになれるとされる。また神様も一つ拾うため、いろりの餅を集めて数えると32個しかないと言われている。
参拝者が男女別に直径約20センチの餅を奪い合う「盗人(ぬすっと)餅」なども行われる。

渡り拍子
高おかみ神社・高梁市
高おかみ神社(高梁市備中町平川)は通称岩谷神社と呼ばれ、渡り拍子が行われている。この渡り拍子は、トビコと呼ばれる4人が一組になり胴丸の太皷が一つついている。この組が7~8組あります。先導の猿田彦2人と2人組の獅子舞が3組、羽織着物の拍子木を打ち鳴らす人数名、2人一組の鐘が数組その他祭りをもりたてる男衆が数名でまさに華やかな一団である。
トビコ達は、袴に襷がけ、あでやかな飾のついた大きな花笠をかぶり、両手には両端に白い紙で切った房をつけたバチを持ち軽快な動きでリズムに乗って踊る。踊りの様子は、大人二人で担ぐ鉦の大きな音に乗って、太皷の周りを跳ねるように踊りながらバチで太皷をポンポンと叩く。
羽織着物の男衆が小さい拍子木でカチカチと踊りの音頭をとっていく。

力石総社
總社・総社市
総社(総社市総社)で8月第4日曜日に「力石総社」という名称で、力比べが行われている。
境内で、半貫から48貫(約180キログラム)の横綱力石までの23個の力石を使った力比べに老若男女が挑む。ルールは、力石を10秒間持ち上げられればクリアで、その最も重いものが記録になる。
平成23年は、横綱力石を42.89秒持ち上げた杉本勝宏さん(奈良県橿原市)が2年ぶり4度目の栄冠に輝いた。女子の部は、32貫を持ち上げた光畑明美さん(長良)が4連覇(10回目)した。

神幸祭
諏訪神社・矢掛町
諏訪神社(小田郡矢掛町下高末)の神幸祭で神輿を駐めて神職がお旅所祭を執行。担ぎ手は神事の間、河原の岩の上で御神酒をいただき一服する。
長閑な山間の秋祭り。

夜の帳が降りた社殿
八幡宮・備前市
八幡宮(備前市鶴海)の9月の夜の情景。ライトに照らされた社殿が漆黒の空をバックに浮かび上がり、備前焼の狛犬が神様をシッカリと守っているように見える。幻想的な風景である。

流鏑馬神事
吉備津彦神社・岡山市
吉備津彦神社(岡山市北区一宮)の秋季大祭(10月第3日曜日)に執り行われる。
流鏑馬(やぶさめ)とは、騎乗した射手が木板の的を弓矢で射貫く神事で、千年以上の歴史がある。この流鏑馬は岡山市指定民俗文化財に指定されており、歴史は古く、康永元年(1342年)の文書に国主が馬や馬費を出した記録があり、少なくともその当時から行なわれていた。
特筆すべきは、吉備津彦神社の流鏑馬においては風水の災いを防ぐ為、風の神、水の神とされる鶴島、亀島の方位に矢が射られることである。

冬の夕暮れ
徳守神社・津山市
徳守神社(津山市宮脇町)の冬の夕暮れの情景。冬の凜とした空気の中、残照に赤く染まる雲をバックに社殿のシルエットが浮かぶ。

千年杉
形部神社 佐波良神社・真庭市
延喜式内社の形部・佐波良神社(真庭市社)の境内に聳える杉の老大木で、県下では五番目の巨木である。根周り10.7メートル、目通り9.1メートル余、樹高は43メートルを越す。幹の根元は谷川を跨ぎ、上部は6本の大枝に分かれ樹勢まだ旺盛で樹齢推定九百年余、土地の人は千年杉と呼んでいる。(昭和34年旧湯原町天然記念物に指定)

無事すぎの輪
見明戸八幡神社・真庭市
見明戸八幡神社(真庭市見明戸)では、毎年年末年始に「行く年、来る年、無事“すぎ”ますように」と願いを込めて、無事すぎの輪で参拝者を迎えている。
ワラを束ねてアーチ状にした骨組みに杉の枝を次々に差し込んだこんもりした緑の輪で、大きさは高さ3メートル、幅4メートル。
雪をかぶった「無事すぎの輪」は特に美しく、「気持ちがいいネ」との氏子さんの声が聞こえたり、帰省した人が家族で参拝し、輪をくぐる姿も目にする。

大イチョウ
福田神社・真庭市
福田神社(真庭市蒜山中福田)の境内には拝殿を挟んで二本の大イチョウがある。
西株は根本周囲8.7m、高さ23m。東株は根本周囲8.7m、高さ26m。樹齢670年とされ、何れも真庭市指定文化財/天然記念物に指定されている。どちらのイチョウも結実しないが、樹勢は旺盛である。
殊に西株は樹冠が大きく広がり、株間には多くの他植物の寄生をを許し、気根も多く垂れ壮観である。

土下座まつり
船川八幡宮・新見市
船川八幡宮の10月15日の例大祭に行われる、いわゆる「土下座まつり」は、正式には「御神幸武器行列」と言われるもので、初代新見藩主関長治候が、新知入国時に祭礼に参内して、敬神崇祖の高揚と領民の安寧、五穀豊穣を祈念するために、公式の「大名行列」を仕立てさせて、船川八幡宮秋季大祭御神幸の先駆をさせたのが始まりで、往時のしきたりを忠実に継承した300年の伝統ある民俗行事として新見市の無形民俗文化財に指定されいる。
総勢64名からなる行列は、白熊と呼ばれる大槍、薙刀、鉄砲、弓、槍、大旗、馬印、沓篭などが主体で、青竹を手にした2人の先払いを先頭に、一定の順路で船川八幡宮と宮地町の御旅所を往復する。
行列が通る沿道の氏子は、清めの盛り砂を作り腰を低くして敬虔に出迎えをする習わしとなっている。
また、この日ばかりは国税庁の特別許可を得て、同宮で醸造られたご神酒(ドブロク)も参詣者に振るまわれる。
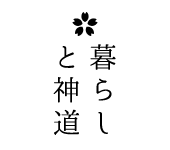



























新野まつりは、毎年11月3日、新野山形の八幡神社(旧山形村・津山市新野山形)を親神様として、二松神社(旧久本、工門村・津山市新野東)、天穂日神社(旧西中村・津山市西中)、天剣神社(旧西上村)、天満神社(旧西下村・津山市西下)の5社、旧6村の氏子たちが、神輿をかつぎ稲塚野の神事場に集まって豊穣の秋の祝い、新野郷すべての人々が喜びを確かめあい励ましあう一郷一所の大祭。 祭りは各社において御霊移しの式を行い、正午に八幡神社の南にある稲塚野に神行します。親神である八幡神社の神輿が、稲塚野の前方にある石鳥居前に到着すると、他の神輿も整列し2頭の獅子を先頭に祭場に向かい、神輿を神座に安置します。祭場では、式典、直会、鍬振り、雅楽演奏などが行われた後、神輿の練りが繰り返される。
近年までは、祭りを執行する家の格式も定まっており、世襲制で行われてきた。祭りの起源の詳細は不明であるが、今日のような姿になったのは、室町期の頃であると推定されている。